
はじめに
『ぼくの昆虫学の先生たちへ』というこの本の内容は、虫好きだった自分の少年時代の記憶を襞の奥まで探りながら現在に呼び出してみるというものです。自分自身の昆虫の世界への没頭、そこから生まれた喜怒哀楽の思いやさまざまな学びがあったのですが、それをただの回想記として書いたわけではありません。
ぼくの虫への興味や関心を掻き立ててくれた「昆虫学の先生」たちを——その中にはファーブルやダーウィンのような専門的な学者もいますし、必ずしも専門家でない人もいます——14人選び、1通ずつ手紙をしたためるというスタイルで書きました。そして現在の自分が童心を思い出し、今とかつてという時間のあいだを自由に往復しながら自然と人間の関係について考えてみました。

トークの会場である店内(UPI表参道)には小川が流れていて木や茂みもあり、アウトドアでキャンプをしているような空気があります。ぼくは昆虫の世界を卒業せず、そのまま山の世界に引き寄せられて、その両方を追い求める時期もありました。というわけで、今回は虫と山、虫とアウトドアを結ぶような話をすることができればと思います。
「アウトドア」という思想をめぐって
そもそも「アウトドア」という用語が日本で使われるようになったのは1970年代のなかばのことでした。この用語には個人的な思いや関わりがあります。先ほども話したように、ぼくは虫好きの少年時代を過ごして中学から山登りをはじめ、それにのめりこんでいきます。
ちょうどぼくが高校生から大学生になる時代、それまで「登山」とだけ呼ばれていた世界にアウトドアという思想がアメリカ経由で入ってきました。それはできるだけ簡素な装備だけをもって野山を歩き、自然からいろいろな学びを得るというもので、背景にはビートニクやヒッピー・ムーヴメントの影響があります。
1976年、山と溪谷社から『アウトドア・スポーツ』(のちにタイトルは『アウトドア』に変更)という雑誌が創刊されます。山と溪谷社はそれまでも『山と溪谷』という雑誌を出していて、登山をするぼくらのバイブルだったのですが、そこが新しい動きを取り込んで紹介しはじめたのです。
そしてこの雑誌に深く関わったのが、日本でアウトドア・スピリットを伝道したパイオニアである作家の芦澤一洋。バックパッキングやフライフィッシングなど一連のアクティヴィティのトータルな意味、道具の一つひとつにこめられた精神性を橋渡しする重要な役割を果たした人です。
ぼくはどちらかというとよりプリミティブな登山文化の中で育ってきたので、「アウトドア」に完全に宗旨替えをすることはなかったのですが、そこに新鮮な思想の息吹を感じ取りました
またそのベースにはヘンリー・デイヴィッド・ソローの哲学があることも直観しました。19世紀のアメリカ、マサチューセッツの森の中で自然と人間の関係について本質的に考え、文明社会が生み出すシステムの暴力性をいち早く批判した思想家です。ソローについて、のちにぼくは『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』という本を書くことになります。

芦澤さんが生まれ育った田舎は山梨県の旧南巨摩郡鰍沢町という富士川沿いの古い河岸(かし)、船舶交易の港街で、そこで彼の自然観が培われました。芦澤さんの著作には『きょうも鱒釣り』というエッセイ集があり、少年時代にその川で父親と魚釣りをした体験を描いたすばらしい文章が収録されています。
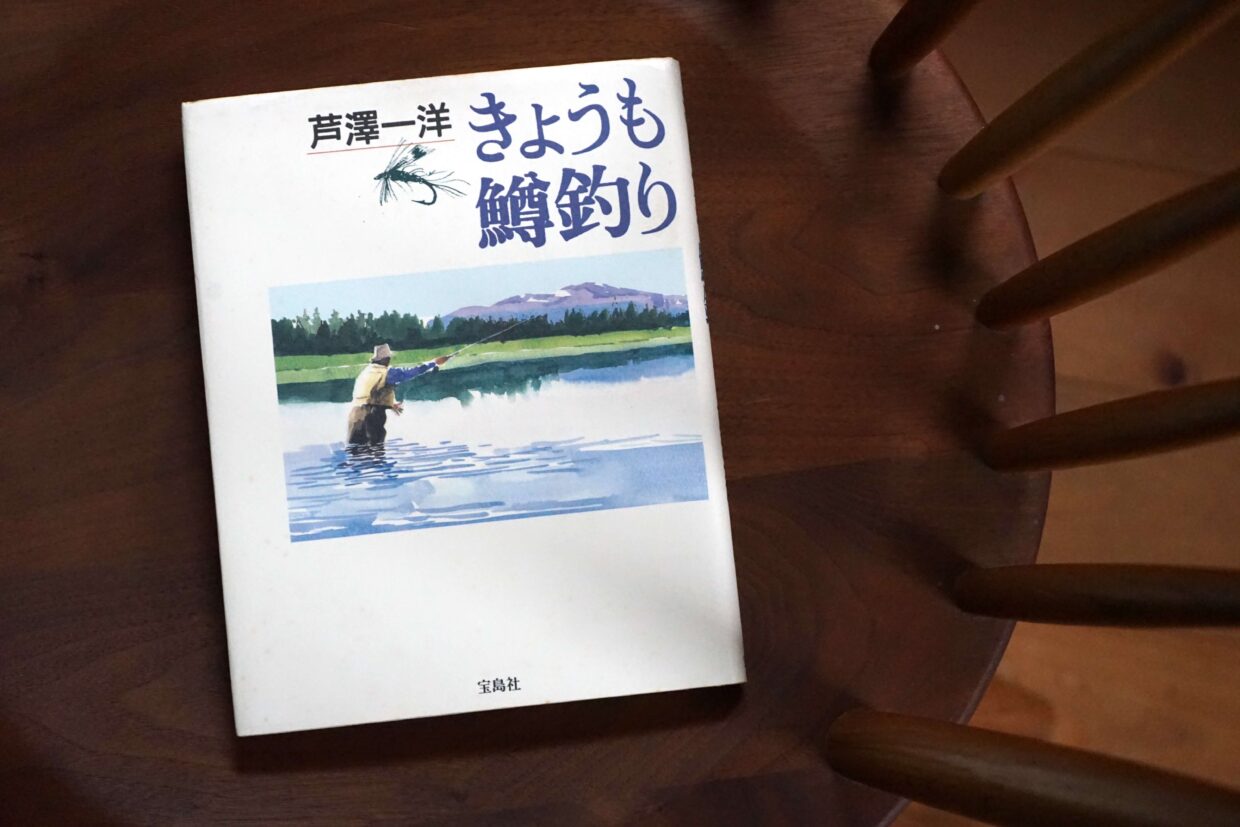
ぼくの母親は旧南巨摩郡の増穂町という隣町の出身だったので、鰍沢にはよく行きました。夏休みになると必ず田舎の祖父母の家に泊まって虫を捕ったり川で遊んだりしていたので、芦澤さんの思い出と自分の思い出はぴったり重なるところがあります。
1976年、芦澤さんは『バックパッキング入門』という画期的な著作を書いて、そこからバックパッカーの文化が一気に流行しだしました。これが日本におけるアウトドア・カルチャーの原点だと思います。

さらにその2年後、コリン・フレッチャーというアメリカの作家による『遊歩大全』を芦澤さんは翻訳しました。「ウィルダネス」、すなわち野生の山や森の中を歩くということに人間の思想の根幹があることを語る内容です。

直接的にはビートニクの作家ジャック・ケルアックの小説『禅ヒッピー(ザ・ダルマ・バムズ)』の影響がみられるこのフレッチャーの本も、おおもとを辿ればソローの哲学に行き着きます。
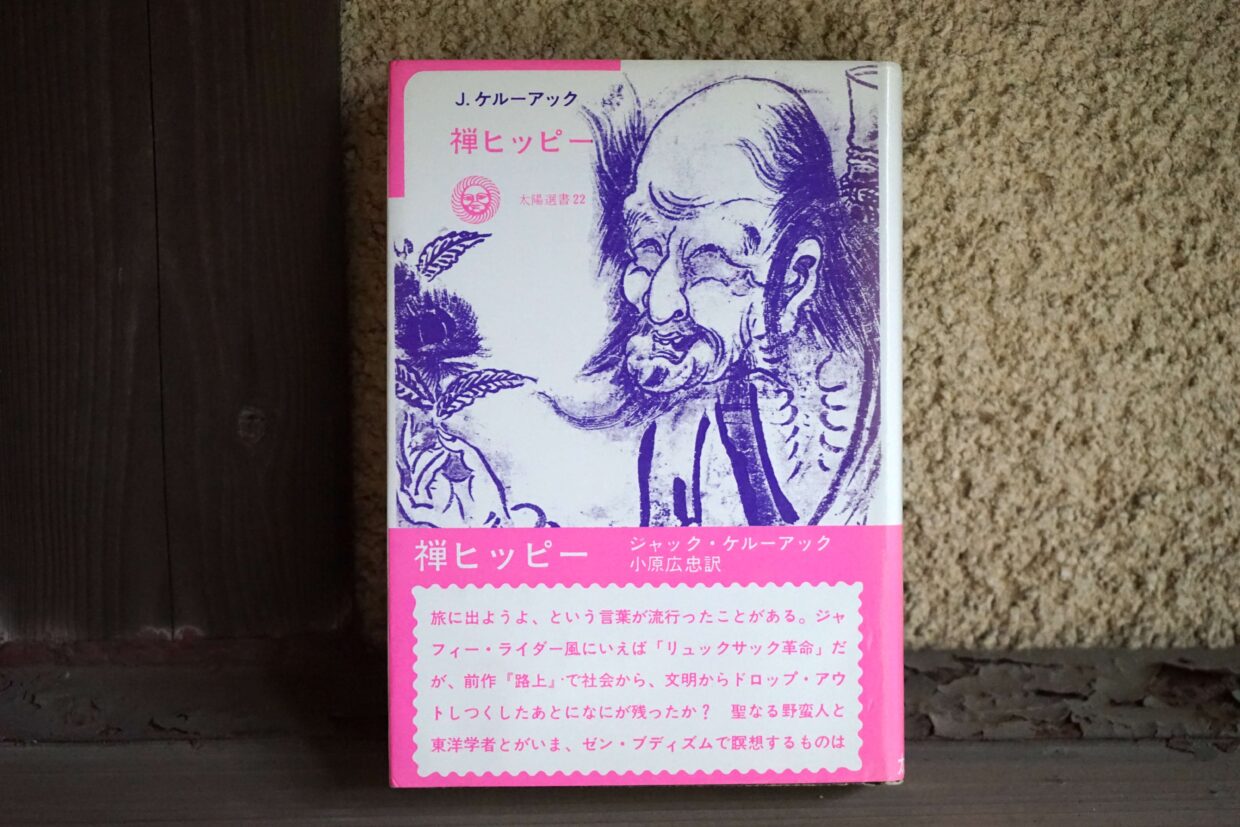
芦澤さんは世代的にぼくよりひと回り上ですが、このようなアウトドア思想の本格的な伝道者が自分と同郷の人間であることをどこかで意識してきたような気がします。
「志賀昆虫」の道具とその謙虚な心
虫の話に移りましょう。『ぼくの昆虫学の先生たちへ』という本に登場する先生のひとりが志賀夘助です。
日本の昆虫採集・標本の道具をほとんど自力で開発して製作し、東京・渋谷の志賀昆虫普及社という店で販売した人で、戦前から日本の昆虫少年たちにとってなくてはならない存在、つまりぼくらの恩人です。

少年時代は虫を捕ることに夢中で、そうした道具を誰が作ったのかということなど考えたこともありませんでした。しかしすばらしい道具の背後にはすばらしい思想があるはずで、今になれば志賀さんがいかに大変な贈り物を手渡してくれていたのかということに気づくわけです。ですから本の中では感謝の思いも込めて手紙を書きました。
「志賀昆虫」でぼくが少年時代に購入し、現在まで愛用しつづけている道具を紹介しましょう。まずはポケット式捕虫網、これは志賀さんがドイツの本格的な捕虫網に新しい発想を加えて開発したものです。
網にはやわらかさ、適度な長さ、深さがあります。そして竹の柄に取り付けられたワイヤの網枠には弾力性があり、8の字に折りたたむと小さくなり携帯することができます。これで空中を飛んでいる蝶などを捕えるのですが、虫捕りの醍醐味はそこにあります。
子どもの頃にはなんとなく地面や木の幹に止まった昆虫にバサッと網をかぶせる動作をしがちなのですが、そうすると隙間から逃げられてしまいます。自分から捕まえに行くというよりは、蝶の動きにこちらの体の動きを同調させると向こうから網の中に入ってくるという感触ですね。

このポケット式捕虫網は、そのしなやかさによって虫と人間の呼吸をシンクロさせ、両者の関係が結ばれる状態を引き出す驚くべき道具です。その他にも標本をつくるための桐の展翅板、グラシン紙、展翅用玉針パール頭付きの虫ピン、採集した虫を保管する三角紙と緑色の三角ケースなどもお見せしましょう……。
志賀さんは明治末期の新潟に生まれ、上京して丁稚奉公のようなかたちで働いた後に昆虫標本の製作会社に入り、虫の世界に目覚めました。このときから志賀さんならではの道具に対するアイデアが次々と生まれたのですが、そこには自然界への深い愛情と謙虚さがしみこんでいます。
ぼくら昆虫少年もまた、どこかでそのことを感じていたと思います。むやみやたらに虫を捕ってたくさん標本を作ってそれを売り物にして、という問題含みのあり方とはちがう思想が道具そのものの中にあったからです。
しかし昆虫採集はよこしまな商品化の世界に飲み込まれる部分もあり、志賀さんは早くからそのことを嘆いていました。ぼくが志賀さんに共感するのはそのためです。
ぼくは今でも過剰な数の虫を捕ることはしませんし、稀少な種に対してマニアックにこだわることも自重しています。マニアになるとどうしても珍しい虫をどこまでも追いかけて、稀少種がいる限られた土地に人間が殺到すれば環境の変化が起こり、当然その虫の数は減っていきます。
志賀昆虫の道具はそれを使うことでぼくらが自然と人間の出遭いの原点につねに立ち返り、自然界をめぐるいろいろな問題について考える謙虚な心を与えてくれるものだと言えます。
パンデミック下の新種の発見
『ぼくの昆虫学の先生たちへ』という本のもとになる原稿を書きはじめたのが昨年2020年の2月ごろでした。ちょうど新型コロナウイルスの世界的拡散と重なる期間、外に出ることを自粛させられる状況の中でかつて自分がどれほど無心に野外で虫を追いかけていたかという思い出を振り返ることになりました。
コロナが自然と人間の接触に関わる野生動物の媒介によって人間界に侵入してきたことを、この間にぼくらは学びました。人間が環境を暴力的に改変することで動物界と人間界のあるべき共存のかたちが崩れ、野生の世界で完結していたウイルスの生活圏がこちらに滲み出してきたということです。
こういう問題をつよく意識しながら執筆を終えて、今年の5月ごろ、書籍用のあとがきに代わる読者への手紙を書こうという時にあるニュースがヨーロッパの東のコソボから飛び込んできました。コソボには湿地帯が多く存在して野生環境がまだ残っていて、多様な種類の水生昆虫が生息する世界的なホット・スポットとして知られています。
そのコソボでまったく新種の水生昆虫が見つかったというのです。それはトビケラの仲間でした。トビケラは羽化して成虫になると陸上に飛び出してきますが、幼虫までは水中で暮らしてイモムシのような姿をしています。
発見をした科学者たちが新種の虫につけた学名は「Potamophylax coronavirus」。この象徴的な名前には、もちろん現在のコロナ禍の最中に発見されたから、という意味もこめられています。

しかしなにより科学者たちが訴えたかったのは、パンデミックが人間社会に襲いかかる猛威に匹敵する自然環境の激しい破壊がこのトビケラたちの生息する水辺の地にも襲いかかっているということです。コソボの湿地帯もまた、生態系が維持されるかどうかぎりぎりの瀬戸際の状態にあることを人間が忘れないためにコロナウイルスの名を与えたといいます。
示唆的な出来事だと思います。そもそも新種の昆虫が発見されるということは自然環境の豊かさを証明すると受け取るのが普通です。
これからもまだ虫の世界では多くの新種が発見されることは間違いないでしょう。昆虫の全種類は100万とも200万とも言われていますが、これは科学的に学名がつけられているものがそれだけいるということです。そうでない未発見の種はその5倍もいるという説もあります。
これは途方もない数で、虫の世界には種の絶滅という問題は存在しないと考えられてきました。しかし実際はそうではないのです。
この本に登場する先生のひとり、写真家でナチュラリストの田淵行男は安曇野を拠点に標高2000メートル以上の高山帯だけに生息する蝶の生態を克明に調査して、その姿を撮影しました。氷河期に北方のシベリアから日本列島に渡来した蝶たちが、だんだん列島が温暖化してきたので高山帯の寒い場所にのぼり、生きながらえてきた種です。
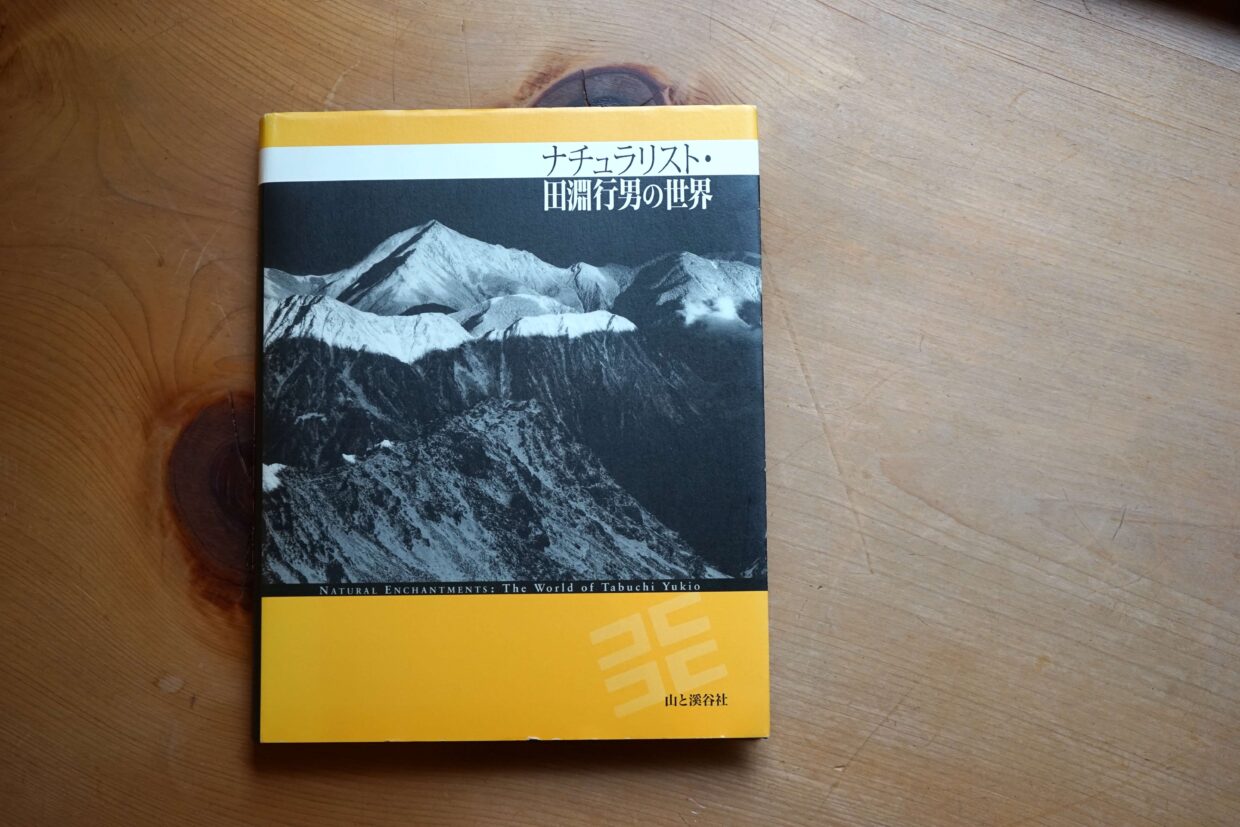
近年の高山蝶の数の減少は、ひどい状況にあります。昆虫の種の絶滅ということが、あきらかにぼくらの身近なところまで押し寄せていることを物語っています。
「全体自然」への感触を思い出すために
トビケラのような水生昆虫の話題が出たので、最後にぼくにとっての「野の教え」の原点にいる偉大な生物学者、生態学者であり思想家、今西錦司の話をしたいと思います。今西さんは登山家としても知られ、日本の近代スポーツ・アルピニズムの草分けで、1940年に名著『山岳省察』を刊行しています。戦後のヒマラヤ遠征でも大きな功績を残しました。

今西さんは西洋的なアルピニズムの精神を日本の側から受け止め、展開しましたが、そこに完全に同一化していたわけではありません。近代日本の山岳思想をつくった彼の原点は生まれ育った京都の北山で、そこはけっして高山ではない、顕著なピークがないなだらかな丘のような地帯です。
今西さんは若い頃からホームグラウンドである北山の沢と尾根と森と峠をめぐり歩いていたのですが、そこには山に生きる木こり、北陸や山陰に行商する人が通る道がたくさんありました。けっして完全な野生の自然ではなく、人間がさまざまなかたちで切り開いた自然の場所でもあったのです。
そのような環境の中で、今西さんは賀茂川上流の沢すじでトビケラと同じ仲間の水生昆虫であるカゲロウという研究対象に出会います。そこから彼の生物学の大発見とも言える「棲み分け論」という、ダーウィン進化論を読み替える新しい理論を導き出します。
今西さんはひとつの川の流れの速いところ、遅いところ、さまざまな環境で生息するカゲロウの種類が違うことを発見します。自然選択説というダーウィンの理論からすると環境の変化は生物に対する支配力のような「圧」として考えられ、生命体は生存競争の中で環境圧に適応することによって進化が起こるということになります。
しかし今西さんはそう考えません。むしろ環境というものは、個々の生物がみずから主体的に認知していくときにはじめて生まれると捉えました。そこに暮らす生物の側にある主体性を与えたわけです。したがって川の流れの速いところ、遅いところに暮らすカゲロウはそれぞれの主体性をもって環境を認知することで、それに合うように自分の姿を変えたということになります。
今西さんはみずからの学問を自然科学ではなく「自然学」と呼びました。自然科学の各分野はそれぞれ「部分自然」しか対象として扱うことができない。昆虫学は昆虫のことしか、植物学は植物のことしか、地質学は土地のことしか研究しない。しかし「全体自然」を扱う学問がなければならないといいます。
今西さんの提唱する自然学は「全体自然」を相手にするものです。昆虫少年が無心のまま捕虫網を持って野原を駆け回り、転んで怪我をしたり毒蛾にやられてしびれたり手や顔を腫らしたりしながら虫の採集をするように、自然からの働きかけを受け止め、こちらからも働きかけるという日々の相互関係の中から「全体自然」への感触は生まれるのだと思います。
今回のトークのテーマである「野の教え」というものを自分がどのように学んだかを考えると、邪心のない昆虫とのつきあいに根ざした自然環境の中で自分が感じていたのは、虫の存在だけではなかったということです。
昆虫を生かしている「部分自然」ではない「全体自然」、それを幼いなりに自分は感受していたのだろうと思います。周辺の土だったり木だったり土だったり川だったりそのすべてを、です。
「野の教え」を伝えることで、「全体自然」への感触をぼくらにもう一度思い出させてくれる今西さんのような先人はたくさんいます。みなさんがそれぞれ自分の関心のおもむくままにこうした先人の足跡や思想を探究してほしいと思いますし、それと同時に、リアルな自然と日々つきあう実践をつづけることで、気候変動やパンデミックという危機的な状況の中からも新しい知恵が生まれる、とぼくは信じています。
【参考文献】
アウトドア文化の理解を深めるための必読書——トーク「希望としての「野の教え」」で紹介された本
- 今福龍太『ぼくの昆虫学の先生たちへ』(筑摩選書、2021)
- 今福龍太『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』(みすず書房、2016)
- 芦澤一洋『きょうも鱒釣り』(宝島社、1995)
- 芦澤一洋『バックパッキング入門』(山と溪谷社、1976[ヤマケイ文庫、2018])
- コリン・フレッチャー『遊歩大全』(芦澤一洋訳、森林書房、1978[ヤマケイ文庫、2012])
- ジャック・ケルーアック『禅ヒッピー』(小原広忠訳、太陽社、1975[原著は、1957])
- 田淵行男記念館・東京都写真美術館『ナチュラリスト・田淵行男の世界』(山と溪谷社、2005)
- 今西錦司『山岳省察』(弘文堂、1940[講談社学術文庫、1977])
- 今西錦司『生物社会の論理』(毎日新聞社、1949[平凡社ライブラリー、1994])
*本稿では割愛しましたが、トークイベントでは、今福龍太さんが『ぼくの昆虫学の先生たちへ』で紹介することのできなかった「先生」のひとりとして詩人・画家の辻まことの名前が挙げられ、彼の著書『虫類図譜 諷刺画集』(芳賀書房、1964)のお話をしていただきました。また、辻まことが寄稿した山の文芸誌『アルプ』を創刊した詩人・思想家の串田孫一や、同誌で連載した文化人類学者の泉靖一らの本のことにも話題が広がりました。
TEXT BY TAKAO ASANO










